日本には古くから季節の節目ごとに様々な行事がありますよね。そのなかで「重陽の節句」という行事はご存じでしょうか? あまり耳慣れませんが七草、桃、菖蒲、七夕と並んで日本の「五節句」のうちのひとつである重要な節句です。
ここでは「重陽の節句」についての由来をはじめ、「なぜ菊をあしらった食べ物を口にするのか」といった素朴な疑問についてご紹介します。
タイトル
重陽の節句の由来|なぜ9月9日なの?

日本の節句はぜんぶで5つ
そもそも節句とは、中国の「陰陽五行説」に由来した日本の伝統的な行事を行う季節の節目となる日です。それぞれの節句ごとに行事をし、その日にまつわる特別な料理を食べる風習があります。
日本の五節句は以下の5つです。( )内の名前は和名です。
- 人日(じんじつ)の節句 (七草の節句) 1月7日
- 上巳(じょうし)の節句 (桃の節句) 3月3日
- 端午(たんご)の節句 (勝負の節句) 5月5日
- 七夕(しちせき)の節句 (七夕) 7月7日
- 重陽(ちょうよう)の節句(菊の節句) 9月9日
「人日の節句」と「上巳の節句」も聞いたこと無いという方もいるでしょうが、これらはそれぞれ「七草の節句」と「桃の節句」のこと。元々は中国から流れてきたものなので、漢名と和名が付いています。皆さんがよく知っている「七草の節句」や「桃の節句」は日本の言い方なのです。
「重陽」と「9月9日」の関係
桃の節句や七夕と比べると、すっかり影が薄い重陽の節句と言えますが、実はとても重要な日です。
古来より、奇数は縁起のいい数字(陽数)、偶数は縁起の悪い数字(陰数)と考えられていて、その奇数が連なる日をお祝いしたのが五節句の始まりでした。
その中でもいちばん大きな陽数である「9」が重なる9月9日を、陽数が重なると書いて「重陽の節句」とし、不老長寿や子孫繁栄を願う行事を行ってきたのです。重陽の節句は五節句の中でも最後の行事として、五節句が定められた江戸時代頃は最も盛んに祝われていました。
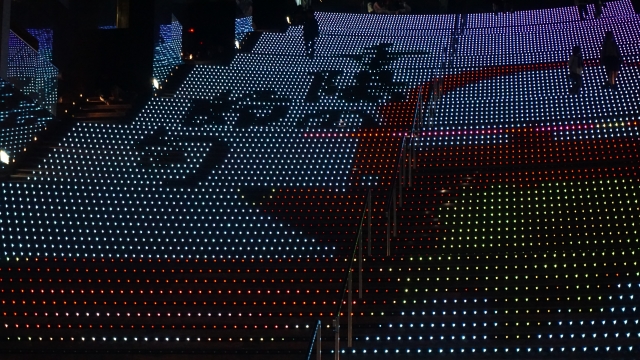
2012年9月、京都駅において「重陽の節句」にちなんだイルミネーションが飾られた
重陽の節句に「菊」が使われる理由とは?
「重陽の節句」が「菊の節句」と呼ばれることは前述しました。この日は昔から、菊の香りを移した菊酒を飲んだり、菊をモチーフにした和菓子を食べることで邪気を祓い、長寿を願う風習がありました。
では、どうして菊なのでしょうか。

重陽の節句の楽しみ方|菊酒、菊湯、菊枕とは?
菊酒や菊の和菓子に始まり、重陽の節句には様々な楽しみ方があります。
- 菊酒 江戸~明治頃までは、菊の花をお酒に漬け込んだ「菊酒」を作っていました。現代は日本酒に菊の花びらを浮かべて菊の香りを楽しむ人が多いようです。
- 菊湯 菖蒲湯や柚子湯と同じように、湯船に菊の花を浮かべて入浴します。こちらも湯気の中に菊の香りがふわりと漂い、風流な気分になることでしょう。
- 菊枕 枕の中に菊を詰め、菊の香りの中で眠ります。リラックス効果がありますし、菊の香りが邪気を祓ってくれるとも言われていました。
- 菊の被せ綿(きくのきせわた) 前日のうちに、赤・白・黄色の綿を菊の花に被せておき、翌朝、菊の香りや露を含んだその綿で身体を清めることによって長生きできるとされています。
- 菊合わせ 昔は庭で菊を育てている家も多く、重陽の節句にはそれぞれ丹精込めて育てた菊を持ち寄って、優劣を競うイベントを行っていました。今でも各地で菊祭りや菊人形展が催されています。
「菊の節句」の豆知識|博多くんちとの関係とは!?
実は、重陽の節句は「菊の節句」意外に「栗の節句」とも呼ばれています。
9月9日はちょうど田畑の収穫も行われる時期であることから収穫を祝う風習もあり、秋の味覚の代表格である栗をもって「栗の節句」とされてきました。また、庶民の間ではこの日を「お九日(くんち)」と呼び、秋の収穫祭を行っていました。有名な「博多くんち」「長崎くんち」「唐津くんち」はこの名残で、「日本三大くんち」として今もなお盛大に祝われています。
重陽の節句で抑えておきたい食べ物や献立
重陽の節句で食べたい祝い膳
桃の節句のちらし寿司や雛あられ、端午の節句の鰹のたたきや柏餅のように、重陽の節句にも祝い膳があります。
お刺身の盛りつけ等によく使われている食用菊は、見た目の美しさもさることながら、優れた抗菌作用で食中毒を防いでくれます。その抗菌パワーが健康や長寿に繋がっているのかもしれません。おひたしやお吸い物、サラダ等に散らしてみてはいかがでしょうか。

菊は「長寿の証」。殺菌作用もあるので料理のつまとしても優秀な存在
「栗の節句」とも呼ばれていることから、重陽の節句には栗ご飯を食べる風習があります。子供から大人まで大好きな栗ご飯はついつい箸が進み、食卓を賑やかにしてくれることでしょう。

写真はさつまいも御飯。甘さや食感などが似ていることから代用する人が多いそう
重陽の節句とは【まとめ】
陽数が連なる9月9日は、五節句の一つである「重陽の節句」に当たります。重陽の節句は「菊の節句」とも呼ばれ、古来より延寿の証とされ、菊の花を飾ったり、菊を浮かべた酒を飲むことによって、邪気を払い長寿を願ってきました。
また、収穫の時期にもあたるこの日は「栗の節句」とも呼ばれてきましたので、栗ご飯を食べるのもいいでしょう(栗は手間が掛かるのでさつまいもを代用する人が多いそうですがw)。
今ではあまり祝われることもなくなってしまった日本の風習ですが、大切な行事のひとつです。今年は菊の花を眺めながら菊酒を飲んで、大人の風流を味わってみませんか。















